「ゴルフが楽しい! でも100が切れない」
ゴルフを始めて数年。人によっては十数年、いや数十年経つのに100の壁をなかなか越えることができないという悩みを持つ人が多いですよね。
そんな人にぜひ参考にしてもらいたい記事を20年あまりゴルフ雑誌の編集をしてきた筆者が書いてみました。
練習する時間がたくさんあれば…とか、最新クラブを買うお金があったら…とか、人それぞれに自分なりの原因はなんとなく分かっているかもしれません。でも「分かっていても100切りできていない」のが現実です。
有名プロ、コーチ、トップアマ、クラブメーカー関係者などで取材してきた経験を生かし、スイングでこれだけは気をつけなきゃいけないこと、効果的な練習法、クラブの選び方、メンタルなど様々な切り口で100切りのコツを紹介しますので、ぜひ参考にしてください!
100切りという数字に意味はある?
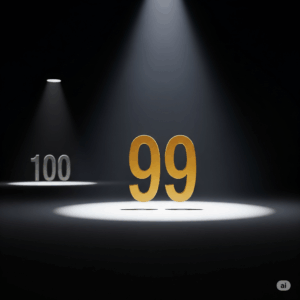
ゴルフコースは、一般的に18ホール(パー72)をいかに少ない打数で回れるか、という競技です。ただ、18ホールを72、いわゆるパープレーでラウンドするのは、プロやかなりの上級者と言えます。普通のアマチュアゴルファーで「上手い」と言われるのは80台で回る人たちで、100を切れば「上出来」とか「まずまずのラウンドだった」と感じるゴルファーが多いと思います(個人的な主観です)
では、その「100」という数字ですが、どんな意味があるのでしょう?
2ケタか3ケタか、という見栄えも1つの要因だと思います。しかし、それだけではありません。一般的なコースのパー72で考えると、100は28オーバーとなり、100切りは27オーバー以内ということになります。この27オーバーというのが大事。18ホールで27オーバーは1ホール1.5オーバーの計算になりますので、2ホールで3オーバー。つまり2ホールに1回ボギー(1オーバー)、もう1回がダブルボギー(2オーバー)で回る、ということになります。
もちろん、1ホールはパー(イーブン)でもう1ホールがトリプルボギー(3オーバー)、あるいは1ホールがバーディ(1アンダー)でもう1ホールがクアドラプルボギー(あまり使わないですね、4オーバーのことです)でも構いません。でも、このレベルのゴルファーはバーディはおろかパーもなかなか出ないと思います。ということは、いかに大叩きをしないかが重要になります。
「100切り」には、他のホールでリカバリーできないような大叩きを何度もしない、という意味が含まれており、それが達成できれば「初心者・初級者からの脱却」となります。
あらゆるスポーツでそうだと思いますが、周りから「あの人は下手」とはあまり思われたくないもの。ゴルフではそれが「100切り」になるんです。
100切りしている人ってどれくらいいるの?

ゴルフダイジェストオンライン(以下、GDO)のアンケート調査(※「100切りは突然に」企画、回答数:7,938)によると、約7割の人が平均スコアで100を切れていないという結果が出ていました。平均スコアなので、100を切ったことがない人の割合ではありませんが、こういうアンケートに答えるゴルファーは、ゴルフにのめり込んでいる中級・上級者が多いと思われますので、全ゴルファーで見ると、かなり多くの人が「100の壁」に当たっているのだろうと思われます。
※引用元
GDO(ゴルフダイジェストオンライン)
初心者GOLF NAVI byGDO<スコア100切りのコツ・100切りを達成している割合と期間
>
https://www.golfdigest.co.jp/beginner/improve/break100.asp
(参照:2025年05月31日)
100切りってどれくらいでできるもの?

前述のGDOのアンケートでは、100切りまでにかかった年数を聞いており、1〜3年が41.7%で最も多く、次いで4〜5年が22.0%でした。1年以内が16.4%いる一方で、6年以上かかった人も2割近くいました。ゴルフを始めたタイミングというのが「コースに出た」なのか「練習場に行った」なのかは人によって違うと思いますが、すぐ切れる人と何年経っても切れない人がいるということですね。
100を切れないことで、ゴルフが楽しくなくなりやめてしまう人も少なからずいるようです。せっかくゴルフを始めたのですから、早く100切りを達成して、もっとゴルフを楽しみたいものです。
100切りの効果的練習法

「ゴルフを始めて何年経っても100切りができない。練習場にも行っているのに…」という人にオススメの練習をお教えします。
ゴルフコーチやレッスンプロに聞くと、そのほとんどが「やみくもに球を打つだけでは上手くなりません」と話します。
プロを目指すような競技者であれば、スイングを完璧にするためにそれなりの球数を打つことが必要なケースもありますが、100切りを目指す人は1度の練習で100球も打てば十分だと思います。1ラウンドで考えれば、パットもあるので100回もショットで打ちませんからね。
「惰性の200球より、目的意識を持って集中して打つ100球」の方が身になります。ちなみに集中して100球打つのは結構しんどいものですが…。
ショット編
色々な練習法がありますが、今回オススメするのは「長めのクラブでわざと曲げる練習」です。これはとあるシニアプロにレッスン取材をした際に聞いた話です。
「真っすぐ打ちたいんだけど…」と思うかもしれませんが、完全な真っすぐに打つのはほぼ無理です。ボールが曲がる要因としてサイドスピンがありますが、サイドスピンがゼロの球を打ち続けるのは、松山英樹プロなど世界の超トッププロでも不可能です。
ちなみに以前、片山晋呉プロが全盛期の(日本ツアーで賞金王を何度も取った)頃、計測したら何球も連続でサイドスピンが1桁、2桁ということがあり、周りは「嘘でしょ」「神がかっている」などの反応で、計測器が壊れているんじゃない?という話にもなりました(実際には壊れていませんでした)
話をもとに戻しましょう。「真っすぐ打てないなら、わざと曲げるってどういうこと?」と思うでしょうが、要は「球が曲がる仕組み」を知ればいいんです。
真っすぐ打とうとしても球が右に曲がる(以降、スライスする)なら、もっとスライスさせてみたり、逆に左に曲げる(以降、フックする)ように振ってみるんです。
右手に力を入れる、オープンスタンスで立ってみる、思いきり上から叩くように振る、左ワキを空けて打ってみる、インパクトの瞬間に球を見ずに目標方向を見て打つ…いろいろ球が曲がる要因がありますが、「これをこれくらいやるとこっちにこれくらい曲がった」ということが分かればいいんです。それがある程度分かれば、球が曲がってどうしようもない時に対応できるようになり、大叩きの泥沼にハマることが減るんです。
まとめると、ショットの練習では、
・真っすぐ打つのは無理ということを理解する
・球が曲がる原因を知っておく
ということが大事ということです。
パット編
先述したとおり、100切りは、9つのボギーと9つのダブルボギーで達成できます。毎ホールパーオン(そのホールのパー数から2打引いた数でグリーンに乗せること)するのは100切りを目指すレベルでは難しいので、全部ボギーオン(そのホールのパー数から1打引いた数でグリーンに乗せること)で考えたら、パット数は45でクリア。でも、全部ボギーオンするのも厳しいですよね。そこを考えると、40パット以内(3パット4回まで、それ以外は2パット)、1ラウンドでパット40切りを目指しましょう。100切りでは、1パットで入れようと思わないことが重要。ファーストパットはカップに「寄せる」ことを目的とし、セカンドパットを「入れる」ようにするんです。
前置きが長くなりましたが、練習法としてオススメするのは、「50センチ、1メートル、2メートルを順番に打つ」を繰り返すといいです。これはツアープロにも教えることがあるティーチングプロから聞いた話です。
「パットに型なし」と言われるように、とりあえずは自分が振りやすいように振って、それぞれの距離感を出してみましょう。振り幅をどれくらいにしたら、それぞれの距離になるのか? 振り幅を変えずにストロークのスピードを変えてみたら、どうなるのか? リズムやテンポを変えたら、距離がどれくらい変わるのか? いろいろ試してみるうちに「グリップはこの方がいい」「スタンス幅はこれくらい」「姿勢はこれが安定する」なども分かってきます。
この練習により、先述のセカンドパットのカップイン率が高まります。また、この応用で、ラウンド前の練習グリーンで、3メートル、5メートルなどもやってみると、ファーストパットがカップに寄る確率を高めることができます。
なかなか実践するのは難しいですが、数分&数セットで構いませんので、できれば毎日(特にラウンド前1週間くらいは)練習すると効果が高まりますよ。
パットの練習では
・50センチ、1メートル、2メートルの打ち方の違いを知っておく
・できるだけ毎日少しだけでいいから練習する
ということが大事です。
100切りのためのクラブ選び

今、どんなクラブを使っていますか? 親や兄弟から譲っていただいたクラブだったり、先輩や友人のオススメ、あるいは店員さんの言われるがままに購入して使っている、というケースもあるでしょう。
スコアの良し悪しは、クラブの要素も大きいです。最新クラブは高くて手が出ない、という人も、中古ショップなどに行けば、1〜2年落ちのクラブが割安で購入することができます。
ただ、何が良くて何が悪いか、わかりませんよね? ここでは、100切りを目指すレベルの人に向けたクラブの選び方を紹介しますが、先に要点をまとめておきますね。
・ドライバーは、ヘッドはもちろんシャフトもチェック!
・フェアウェイウッド&ユーティリティは、ドライバーと同じモデルを!(優先順位低め)
・アイアンは、少し重いかな?くらいでちょうどいい!
・ウェッジは、バンス角に注目!
・パターは、しっくりくれば何でもOK!
・ボールは、将来のことを考えるとスピン系がベター!
ウッド編
まずは、ウッド。ドライバーやフェアウェイウッド、カテゴリー的にはユーティリティも入ってくるでしょう。これらのクラブは飛距離を出すことが目的で、ティショットや残り距離が長い2打目以降に使用しますよね。
とりあえず、パー3以外のホールのティショットでは、ドライバーを使うことがほとんどだと思いますので、ドライバーはマストアイテムです。そのドライバーの選び方というと、以前は「ゼクシオを買っておけば間違いない」とか最近は「ピンが曲がらずに飛ぶ」と言われていました。ただ、正直いいますと、主要メーカー(ピン、キャロウェイ、テーラーメイド、タイトリスト、ダンロップ、ブリヂストン、ミズノ、ヨネックス、プロギア、オノフ…)のここ数年のモデルであれば、問題ありません。100切りを目指すレベルであれば、それほど違いを感じないと思います。(もちろん、いわゆるプロスペックは扱いが難しいので、やめてくださいね)
問題はシャフト。ヘッドが同じでもシャフトによって全く別のクラブになる、と言っても過言ではありません。あまりにも種類が多いので、こればっかりは実際に試すのが手っ取り早いです。ショップやシャフトメーカーが試打会を頻繁に実施しているので、行ってみるとオススメを教えてくれます。実際にシャフト試打会の現場で取材した際に、参加者の人が「WEBや雑誌を見て、これが良さそうと思っていたものが合わず、まったく眼中になかったものがすごく合ったんだよ」と話していたことが何度もありました。
ちなみに、フェアウェイウッドやユーティリティは、100切りだけを目指すのであれば、なくてもいいクラブです。ティショットはドライバー、第2打以降はアイアンと決めておけば、フェアウェイウッドやユーティリティは使いません。パー5の2打目がしんどいって思うかもしれませんが、ボギーオンでいいと思えば、2オンを狙う必要はまったくなく、アイアンで2〜3打でグリーンを狙えばいいんです(無理と承知で2オンを狙うのもゴルフの楽しみ方の1つですが、ここはあくまで100切りを目指すことに焦点を当てています)
どうしても、入れておきたいと思う人は、ドライバーの流れ(同じメーカーの同モデル、シャフトも同じ)で合わせるといいでしょう。
アイアン、ウェッジ編
次は、アイアンとウェッジについてです。
アイアンやウェッジは、1本あたりの単価はドライバーなどと比べて安価ですが、5本とか7本のセットになり、トータルすると高価になりますので、おいそれと買い替えができませんね。
そこで、選び方のポイントですが、ドライバー同様、主要メーカーのここ数年のモデルであれば、基本的に問題ありませんが、アイアンはドライバー以上にレベル差がありますので、いわゆる上級者モデルを選ばないようにしましょう。
打点が安定しないので、「フェース面は大きい」方がスイートスポット(エリア)も広くなります。また、「ソールが分厚い」方が地面に刺さりにくく(いわゆるダフリにならず)滑ってくれて振り抜きやすいです。そして、いわゆる「飛び系アイアン」を使うといいでしょう。アイアンは飛ばすクラブでなく、狙うクラブですが、100切りを狙うレベルのゴルファーは、打点が安定せず飛距離が出ないことが多く、それが力みにつながるからです。元々飛ぶクラブだったら、それも解消しやすいです。
また、シャフトを含めた重さもチェック。試打などで実際に振ることができれば、体がぐらつかない程度でできるだけ重いものがいいと思います。体がぐらつくほどの重さがあるとスイングが安定しませんし、軽すぎるといわゆる手打ちになりやすく、これまたスイング軌道が不安定になるからです。
ウェッジに関しては、アイアンとセットのものがいいと思います。(別売のこともありますが、同じシリーズの方がいいです)いわゆる単品ウェッジだとロフト角もバンス角も選び放題と言えるほど色々種類がありますが、アイアンからの重さやロフト角の流れなど、ちゃんと考えないといけないからです。
どうしても単品ウェッジにしたい、ということであれば、そのあたりを考慮しつつ、バンス角が大きめ(10度以上)のモデルを選ぶようにしましょう。特にバンカーショットの成功のカギはバンスの使い方にあるからです。(ここはちょっと難しい話になるので、別記事にまとめようと思います)
パター、ボール編
パターに関しては、スイートスポットが広い、ストロークが安定する形状など様々な特長のあるモデルがあり、値段もピンキリです。
値段が高いものにはそれなりの理由がありますが、高いから入るというわけではありません。実際に中古ショップで1,000円程度で買ったパターで何千万円も稼いだというプロもいると言います。
上級者やプロがよく言う話で、パターに限ったことではありませんが、「このクラブの顔が気に入っている」と言う話があります。要は「違和感なく構えやすく、思った通りに始動させることができる」ということです。この感覚は100切りを目指すレベルでも実感できるもの。
ですから、とにかくたくさんのモデルを試すのをオススメします。ショップに行って、色々な形状のパターを手に取り構えてみてください(試打できれば実際に打ってみてください)すると、「これ打ちやすい」というモデルが見つかりますよ。パター選びはこの感覚がとても大切です。
ボールもスピン系、ディスタンス系と色々あります。一長一短がありますので、どれを選んでも良いのですが、将来的なことを考えたらいわゆるスピン系を使った方がいいと思います。(これは完全に個人的な見解です)
ディスタンス系の方が飛距離が出るので、楽にグリーンまで運べます。ただ止まりません。せっかくグリーンにオンしたと思っても、ゴロゴロとコロがってグリーンの奥へ、なんてことが良くあります。もちろんそのコロがりも想定した上で打てばいいのですが、グリーンの傾斜や芝目により想定しにくいものです。
また、100切りを卒業して、次の目標(90切り、80切り)などを目指す際には、スピンで止めることが必須級になり、ボールはスピン系一択になるからです。スピン系とディスタンス系は結構違うので、スイッチするのに結構苦労するケースがあります。それを考えると、最初からスピン系を使った方がいいのかな、と思います。
問題点を上げるとするなら、スピン系の方が相対的に値段が高いということ。OBや池ポチャなどでボールを失くすことが多いことを考えると、ひとまず100切りはディスタンス系のボールで、と考えるのもコスト優先であればそれもありです。
100切りのためのコースマネジメント

コースマネジメントと聞くと、プロや上級者がやるイメージがありますが、これを意識することで、100切りにも近づきます。
ここでは、広義のコースマネジメントとして、メンタルなことも含めて技術的なことじゃない考え方など、実際のコースで気をつけたいことを紹介します。
ショット編
ショットに関しては、自信過剰にならないことが大切です。同伴競技者に影響され、林越えのショートカットを狙ったり、池越えの2オンを狙ったり…。どんなショットも謙虚にいきたいですね。
それを踏まえて、ショットの狙い目の考え方を紹介します。これもとあるコーチから聞いた話ですが、狙う方向で「◯」「△」「×」を決めます。例えば、ティショットでフェアウェイ真ん中が「◯」左が「△」右は「×」としたら、右には絶対行かないようにする。やや左めにターゲットをとり、右に曲がらない(左に曲がる)球を打つ。そうすれば「×」の右には行かない、という寸法です。
先述したように、100切りのためには、バーディやパーを狙うよりも大叩きを未然に防いでトリプルボギーを叩かないように考えましょう。
メンタル編
メンタル面で気をつけたいのは、何事も「過度」に考えないこと。ミスを引きずりすぎる傾向があり、ミスがミスを呼ぶので、次のショットではそのミスをいい意味で忘れましょう。切り替えるっていうことですね。ちなみにまったく気にしないのは同じミスを繰り返してしまうので、それはNGです。
「切り替えが難しい」と思う人は、30秒だけ「どうしてミスをしたのか」その原因を考えましょう。そしてその原因を「次にしないように気をつけよう」と強く思うのです。30秒後にはミスしたことを振り返らないこと。これで「またミスったらどうしよう」という悲観的な考えから「今度はこうならないようにスイングしよう」と前向きな考えになります。
切り替えに関しては、とあるメンタルトレーナーの話として、次のようなものもありますので、参考にしてください。
『周りの景色でも見て「あんなところに花が咲いている」「あの山はなんていう山だろう?」などゴルフとはまったく違うことを考えると、切り替えやすい。後は、無理やりでも口角を上げ、笑顔を作るのもいいよ』
トラブル編
たくさん練習してきても、林の中に打ち込んだり、バンカーや深いラフに入ったり、トラブルはつきものです。
そこで、何が重要かというと、次のショットだけで挽回しようと思わないこと。トラブルの後はカッカきていることが多く、冷静な判断ができないもの。一か八かで勝負にいくとほぼミスして、泥沼にハマってしまうのがオチです。
とあるレッスンプロの話を思い出しましたが、トラブル時は「同じ状況で10回打ったとして8回成功する自信のある脱出ルートを考えましょう」というのがいいと思います。ミスしている分、少しでもグリーンの方向に打ちたい気持ちもわかりますが、その気持ちで普段のスイングができなくなっていることが多々あるからです。
また、その脱出ルートで行った際の最悪のケースを考え、それに対応した打ち方をしましょう。例えば林に打ち込んだ際、安全だと思った真横に出すルートでザックリして林から出せない、ということもありえます。これを想定すれば、ザックリよりトップ目で強く打った方がいいという具合です。もちろん、打ちすぎで逆サイドのラフまで行ったとしても林の中からもう一度打つよりはスコアは崩れません。
100切りのためのコツ(番外編)
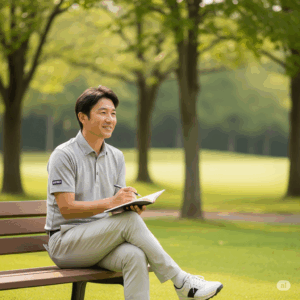
ここで、100切りをするためのちょっとしたコツを紹介します。
今まで書いてきた、自分に合ったクラブを使用し、ある程度練習し、ラウンド時のマネジメントができることが前提で、「これをするといいかも!」的な話になっています。
前日編
「明日は待ちに待ったラウンド! 時間もあるし、練習場でも行くか」という人も少なくないでしょう。もちろん、行くことは否定しませんが、注意点があります。
それは、事前に球数を決めておくこと。よほど体力がある人なら別ですが、100切りを目指すゴルファーのほとんどは、球数が多くなると疲れてスイングが不安定になるからです。
スイングが不安定になる→球がばらつく→どうすれば治るだろうと思う→治そうと必死になって球数がどんどん増える→疲れる→さらにスイングが不安定になる。
こういう悪循環が生まれてしまいます。さらにそのまま帰ると、その原因が気になってよく寝れない、なんてこともありますので、注意してください。
ちなみに、前日に練習するなら、オススメはパットの練習。体力的にもそこまで疲れませんし、「明日はこうやって距離感を出そう」という最終チェックができるからです。オススメというより、ラウンド前日の必須事項と言っても過言ではないので、ぜひ試してください!
当日スタート前練習編
ラウンド当日のスタート前の練習についてお話します。
絶対必須なのはパットの練習。特に家でできない長めの距離の練習をしましょう。
まず、最初は家でやっている、50センチ、1メートル、2メートルを順番に打つ練習をして、家のマットと実際の芝との違いを把握しておきましょう。そこから徐々に距離を伸ばしていきます。その際カップを狙う(入れる)必要はありませんので、できるだけ平坦で真っすぐのラインで打てる場所がベターです。
パット練習を切り上げる最後は、1メートルくらいの距離をカップに入れる練習を。「カップに入れる」感覚を持っておくと、ラウンド時にいいイメージが沸きやすいです。
ショットの練習は、疲れない程度にウォーミングアップとして行いましょう。なんとなく「今日は右にいきやすいかな」「いつもより球が上がらない気がする」などの傾向を感じればOK。無理にスイングを修正すると、訳がわからなくなるので絶対NGですよ。
球数に余裕があれば、そのコースのパー3のティショットで使用しそうなクラブをティアップして打っておきましょう。パー3はティショットがグリーンに乗れば、スコアメイクが楽になりますので、練習場でそのイメージを作っておくのは悪いことではありません(やり過ぎると逆にプレッシャーになるのでほどほどに!)
ちなみにバンカー練習場があれば、やっておいた方がいいです。実際に砂から練習する機会があまりないと思いますので、砂の硬さを含めて、チェックしておきましょう。そして「どうしてもバンカーは難しい」と思ったら、ラウンド時には徹底的にバンカーを避けるマネジメントをして下さいね。
当日昼休憩編
日本のゴルフは、ハーフラウンド後にランチ休憩が入ることが多く、ゴルフ場の混み具合にもよりますが、食事後に時間が余るケースがたびたびあります。
ハーフで体力的に疲れていたら、軽いストレッチ等をしながら余計な体力を使わないで休みましょう。
体力的に問題がなければ、練習グリーンでパットの練習をすることが多いでしょう。
※練習場が使えることもありますが、競技の場合は色々な規則で違反になることがあります。ここでは100切りを目指すゴルファーに向けての話なので、あまり関係ないと思いますが、コンペ等だとそういうことにうるさい人も多いので、気をつけましょう。
パットの練習も漫然にやると、よくありません。前半ハーフで課題があったなら、ここで修正しておきましょう。特別に課題がなければ、遊び感覚でできる練習法を紹介するので、試してみて下さい。
球を2つ用意し、まずは1球打ちます。そして同じところから1球めにジャストタッチで当たるように打つ。同じところを狙って同じように打てば同じところにいくはずですが、長い距離になるとなかなか当たりません。これを繰り返すと、ストロークがより安定するでしょう。当たると嬉しいし、外れると悔しいので、楽しく練習できます。これで悩んで後半スタートになるのは良くないので、程々の距離で試すのがオススメです。
ちなみにお酒をたくさん飲んでしまう人も多いですが、100切りを目指すなら、それも我慢。少しであればいい気分転換になりますが、飲みすぎると体のブレ、集中力の低下などいいことはありませんよ(特に車を運転する人は、少量でもアルコールNGにしましょう。後半ハーフ&お風呂だけではアルコールが抜けないことの方が多いです! 事故を起こしてからでは遅いですよ!!)
まとめ

いかがでしたでしょうか? 100を切るためのポイントとして以下を話してきました。
・バーディ、パーは狙わない。トリプルボギー以上打たない。
・ショットの練習は真っすぐ打とうとしない。
・パットの練習はできるだけ毎日行う。
・クラブ選びにはコツがある。
・当日は自信過剰にならず、大叩きしないコースマネジメントする。
・練習グリーンは念入りに。
・昼休憩のお酒の飲み過ぎはNG などなど…
「こんなたくさんやるのは無理!」と思うでしょうが、これらをすべてやらないと100切りできないわけではありません。
まずは、1つ試してみてください。それでも100を切れなかったら、別のものを1つ試す。自分が気になることを試すんです。それを繰り返していくうちにいつの間にか100を切ることができ、今度は90を切ることが目標になるなど、楽しいゴルフライフが待っていますよ!
100切りするためのコツは、これからもアップするつもりですので、他の記事も見にきてくださいね!
早々に皆さんが100を切ることを祈念しています!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!!
※写真は全て生成AIで作成しました。

コメント